| |
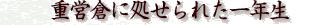 |
|
ある朝、整列のラッパが鳴り全員武装して、宿舎に当てられていた公学校の校庭に並んだ。何事かと緊張する我々の前に、カッと目を見開いた中隊長が仁王立ちになり一同を睨み回すと、2人の学徒兵を面前に引き出した。
「貴様らは中隊長の顔に泥を塗りやがった。俺が征伐してくれる。そこへなおれ」と言うや、ヘタヘタと座り込んだ兵の頭上に、いきなり腰の軍刀を抜いて振り上げた。白刃が朝日に光る。裂帛の気合と共にそれを振り下ろす。どの顔もどの顔も恐怖に引きつって声もない。次の瞬間、刃は学徒兵の細首をなぜて腰の鞘に納まっていた。
この中隊長は、ビルマ戦線の生き残りだと言う中尉で、顔も体も迫撃砲弾を浴びたと言う傷跡で、すさまじくひきつり、見るからに恐ろしい軍人だった。
|
|
|
この中隊長が我々の前に姿を見せたのは、入隊以来、このときも含め3度しかなかった。普段は特設の宿舎に何処からか連れて来た女と当番兵を侍らせて、酒色に明け暮れていたと言う噂だった。
2人の兵は、2週間の重営倉(軍隊の監獄)に処せられ、台北にある憲兵隊本部に連れて行かれたと言う事だった。一体何をしたと言うのだろうか。恐る恐る伝わってきた話によれば、この2人は公用で外出した際に、母親に当てた手紙をポストに入れたのが憲兵に見つかったのだそうだ。
兵隊には、軍事郵便と言って隊を通じ検閲を受けた郵便以外は禁じられていたのだが、そんな事は我々も良く知らなかった。ましてこの2人はまだ一年生、16歳か17歳でしかない。お母さんが恋しい歳ではないか。「お腹が空いた」とか「作業が辛い」とか、そんな事ばかり書いてあったと言う。 |
|
|
