| |
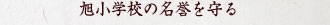 |
学校では、言葉の違う所為もあり珍しがって何かと特別に扱ってくれたが、私は、瞬時も自分が旭小学校の生徒であると言う事を忘れなかった。勉強でもなんでも旭小学校の名誉を傷つけてはならない。田舎の子供に馬鹿にされてはならないと、いつでも心の隅で思っていた。
服装は、祖母が町の洋服屋で季節にあったものを上から下まで揃えて買って下さった。文房具もかばんもすべて新調して下さった。
台湾では半ズボンだったのが、ここでは長ズボン。靴はなくて下駄、雨の日は足駄に唐傘。子供たちは着物姿が主で、洋服を着ているのは比較的裕福な家庭の子だった。かばんもランドセルではなく肩から斜めに提げるズック。何から何まで異文化の世界だった。 |
|
|
小学校は町の中心部にあって徒歩15分ほど。広い屋内体操場を抱えた2階建ての木造であった。鼻の下に2本棒垂らしたガキ大将らしいのが「ウナァどこから来ただ」と寄って来た。「台湾から来た」と言うと「何、台湾てどこだえ」と不思議そうにした。クラスで威勢を張っていたのは、町長で蒲原鉄道の社長の息子だった。早速子分を引き連れて私の家を見に来た。「俺の家にも来い」「お前、洋館見たことあるか」と言う。なるほど当時の村松には唯一だっただろう、資産家らしく、文明開化を思わせる洋風の2階屋が中庭に建っていた。
台北は、学校も主だったは官公署も、ほとんどが鉄筋コンクリート、町並みはレンガ造りで、はるかに近代化されていて、内地の田舎町とは比べ物にならない大都会だったので、村松では、すべて何十年も昔に帰った感じであったが、ここの連中は台湾と言うと、余程未開の土地とでも思っていたようだった。 |
|
|
