| |
台湾の日本人の家庭では老人の存在が稀だったので、封建的な気風が比較的薄かった。それに父母が、当時としては珍しい恋愛結婚であったせいもあり、我が家では、子供たちも男女夫々に家事を分担し、父も時により平気で台所に下りた。
それが、ここでは、父も祖父母に気を使い、特に母は祖母の一言一言にピリピリしていた。若い私などには、どうにも理解できない事態だった。
夜、寝静まってから母に「お前にばかり苦労をかけるなぁ」と父が寝物語に言っていたのを聞いたのが、せめてもの慰めだった。 |
|
|
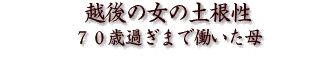 |
母には泣いている暇はなかった。強くならざるを得なかった。私に向けたあの厳しい言葉も、その心底からの叫び、やり場のない感情の吐露であったろう。
母は、その後30年、70歳過ぎるまで、生命保険の“ニッセイ”の小母さんとして、あの雪国で働き続け、近在の有名人になった。村松近郷何処へ行っても、顔見知り「アッカ、おまんかね、今日は何用だね。まあお茶飲んで行きないや」と言う按配である。就職の世話、嫁の世話をし、仲人をした数はかぞえ切れぬと言う。弱々しかった母の何処にそんな力が潜んでいたのか不思議な話だ。
越後の女の土根性・模範と言って良いだろう。 |
|
|
