| |
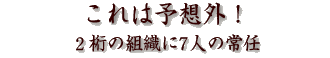 |
京浜急行で川崎の次の駅「八丁畷」で降りる。鄙びた駅である。田舎にしては緑に乏しい、殺風景な町並みだ。線路際を5分ほど歩いて、指示された2階屋の寮に着く。
その2階の20畳ほどの広間の一隅が、当分の間の私の事務所兼寝所となる。身の回りのものは、朝鮮戦争以来の半非公然の生活で大半は散逸して、せんべい布団の上下とリュックサック一つだけの身軽さである。
出迎えてくれたのは、党県委員会青年対策部長のD。彼は、私が青年共産同盟の本部に入った当時の中央書記局のメンバーのひとりで、顔見知りだった。 |
|
|
懐かしい気もしたが、Dのような言わば青年運動生え抜きの人物がいるのなら、あえて私が派遣される必要もなかったのではないかと、変な気がした。
更に、Dの紹介で7人のいずれも県民青の常任と言う同志たちと初顔合わせ。一人は県委員長、横浜地区担当が4人、川崎地区担当が2人。聞けば、組織現勢は2桁台、班らしい班は数えるほどしかないのが実態と言う。この僅かな組織に、これだけの陣容は明らかに過剰で、常任として毎日どんな活動をしているのか不思議だ。
予想外の展開に戸惑うばかりだった。 |
 |
| 7人の常任活動家は、全員レッドパージや企業整備で職を失い、失業保険の受給中で、空いた時間には失業対策事業で稼いだりしていて、常任とは名ばかり。 |
|
|
